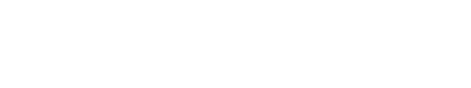運動神経が破壊されていく、神経障害の難病
四肢、舌、喉といった部位の筋肉が痩せていき、筋力が低下する神経変性疾患。1年間に人口10万人あたり1~2人が発症するとされ、中高年が好発年齢といわれる。男女比では、男性の発症が女性の2倍程度となっている。
進行するスピードが速く、発症後3年から5年で罹患者の半数ほどが呼吸筋麻痺に至り、死に直面するとされる。原因としては遺伝的要因を中心にいくつかの説があるが、確かではなく、現状では根本的な治療法も存在しない。
症状
●筋肉の委縮 ●筋力の低下 ●攣縮(れんしゅく:手足がぴくぴくと痙攣する) ●嚥下障害 ●構音障害 ●開口不全 ●歩行困難 ●呼吸困難
治療法
興奮性神経伝達物質の投与:病気の進行を遅らせる
睡眠薬、精神安定剤の投与:不安・不眠を改善する
鎮痛剤の投与:痛みを取り除く。末期には緩和医療も用いる
胃ろう・中心静脈栄養:嚥下障害がある場合などに適用
人工呼吸器:呼吸筋まで麻痺が進行した際に装着する
薬物療法:リルゾールが呼吸不全までの期間を延ばすために投与されることがある(本症に対して唯一認可されている薬)
高齢者には注意が必要です!
①飲み込みにくい、話しづらいといった症状から発症する例が多いとされ、この場合、症状の進行も早いといわれる
②人により経過が異なるので、ケースに沿った対処が必要
アセスメントのポイント
●栄養状態、運動機能障害はどうか
●胃ろう造設、気管切開などについての本人の意思確認
●家族などの介護環境、社会資源はどうか
今後の見通しと支援
ALSは、根本的な治療法はなく、進行にあわせた対症療法を行っていきます。重度の身体障害が進む一方、知能や記憶力、知覚神経、眼球運動や意識は末期まで鮮明に保たれます。QOLの向上という視点をもった援助が必要です。
日常生活の留意点
●利用できる公的支援について、早い段階で申請できるように支援します
●杖、手すりの設置などで移動を支援します
●残存能力に応じたコミュニケーション手段を確保します。意思伝達装置などについては、高齢者の場合、操作に不慣れなことも多いです。使用方法などを専門家とも相談し、円滑に利用できるように支援します
●嚥下障害の対応のため食べやすい食形態の工夫をします
医療連携のポイント
●進行に応じたリハビリテーションの評価
●家族や介護職員が経管栄養や痰の吸引を行う場合の指導